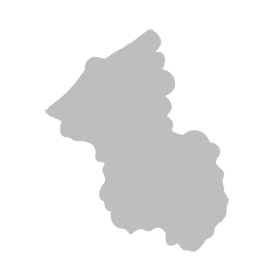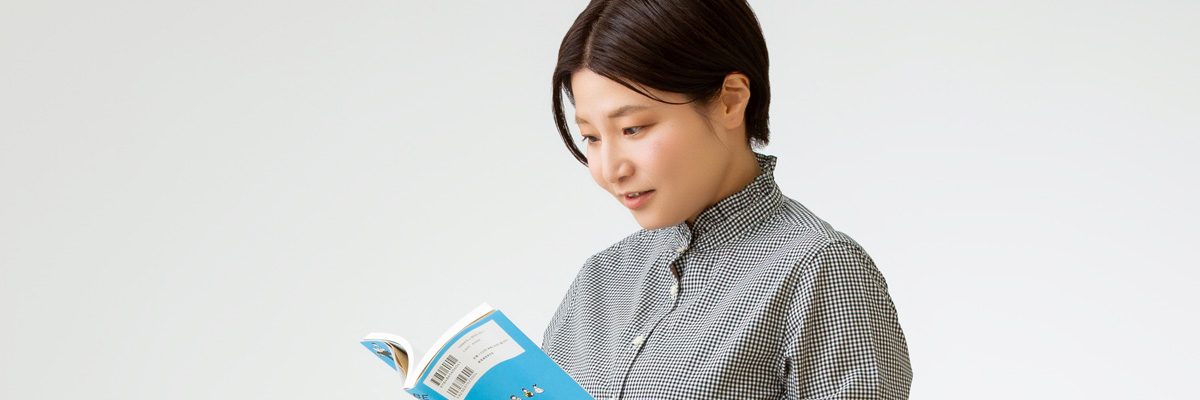加賀市の現状
kagastatus
いま加賀市で起きている課題や変化を、現場の目線で見つめ直します。

人口減少と少子高齢化
加賀市では、若い世代の市外流出、出生数の減少、高齢化が進んでいます。
空き家や耕作放棄地の増加、地域サービスの縮小といった影響は、まちの活力そのものに関わる問題です。
これまでの取り組みが積み重ねられてきた一方で、地域の実情に即した対策をさらに深める余地があるのではないでしょうか。
中心部と周辺部では人口減少のスピードや課題が異なります。
空き家のリノベーション、小規模コミュニティ支援、地域交通の維持など、細やかな対策をどう進めるか。
「一律の施策」では届かない声に耳を傾けることが必要ではないでしょうか。
働く場の確保、子育て支援、教育環境の充実。
若い世代が「地元で暮らしたい」と思える要素を増やすことは、地域の持続可能性に直結します。
一人ひとりの声を聞き、柔軟な支援や制度を検討する余地はまだあるのではないでしょうか。
人口減少は単に「数」の問題ではなく、つながりの喪失にもつながります。
地域の集まり、助け合い、声かけといった小さなつながりを支える仕組みこそ、これからの地域力の土台ではないでしょうか。
数字の回復だけではなく、「心のあるまちづくり」を考えていきたいと感じています。
観光と経済のこれから
山代、山中、片山津の温泉地は、加賀市を代表する観光資源です。
これまで多くの方に支えられ、加賀の魅力を発信してきたことは、大きな誇りです。
一方で、観光業への依存度の高さ、景気や社会情勢の影響の受けやすさ、伝統産業の後継者不足といった課題は、これからのまちづくりを考えるうえで重要なテーマではないでしょうか。
観光客数はコロナ禍から回復傾向ですが、「その経済効果が地域に広く届いているか」という問いは残ります。
若者の働く場、地元農産物や工芸品の流通、地域事業者との連携など、利益が地域内で循環する仕組みをさらに育てていけるのではないでしょうか。
温泉、工芸、食文化。
受け継がれてきたものを大切にしながらも、新しい観光の形や体験を生み出す挑戦も必要です。
若い感性や外からの視点を取り入れる場をつくること、それもこれからの加賀市にとって大切ではないでしょうか。
観光は外から来る人のもの、ではなく、地域の人が誇りを持てるもの。
観光で得た知恵や収益が、地域の子ども、高齢者、働く人たちの暮らしにも還元されていく。
そんな「観光と暮らしの架け橋」を考えていけたらと感じています。
教育と人材育成
加賀市の教育は、地域の未来をつくる基盤です。
少人数学級の導入や教育現場の改善など、これまでの取り組みは大切な一歩です。
ただ、現場の先生たちの負担感や、子どもたち一人ひとりに目を向けきれない状況が残っているのも事実ではないでしょうか。
教員の過重労働や人手不足は全国的な課題ですが、加賀市でも深刻です。
教材準備、保護者対応、部活動、心のケアまで背負う現場の先生たちを、どう支えるか。
外部人材や地域ボランティアの活用など、さらに工夫の余地があるのではないでしょうか。
地元の企業や農家、福祉施設、文化団体と連携し、学校外の体験を広げる試みも始まっています。
これをさらに進めることで、子どもたちが加賀の魅力を知り、地元への誇りを育めるのではないか。
学校と地域が一緒に学びをつくる、その可能性を広げていきたいと考えています。
教育の主役は、子どもたち自身です。
学校に何を感じ、何を求めているのか——その声を聞く仕組みは十分でしょうか。
アンケートや子ども会議、対話の場をつくり、「子どもたちと一緒に学校を育てる」視点をもっと広げていけるのではないでしょうか。
働く環境と生活の両立
加賀市では観光業、製造業、医療・福祉分野など、地域を支える仕事が多くあります。
一方で、非正規雇用や低賃金、長時間労働といった課題を抱える方の声も聞かれます。
「仕事と暮らしが両立できるまちかどうか」は、地域の魅力を左右する大切な問いではないでしょうか。
テレワーク、副業、フリーランス、短時間勤務など、都市部では広がっている柔軟な働き方。
加賀市でも、子育てや介護と両立できる選択肢を増やし、地域の人材が力を発揮できる環境を整える余地があるのではないでしょうか。
地元で働く機会を増やすには、若者や女性の就労支援、地域起業や小商いのサポートも欠かせません。
働く人が安心して挑戦できる仕組み、さらに強化していけるのではないかと感じます。
働きやすさは、そのまま暮らしやすさにつながります。
働く世代が安心できるまちは、高齢者も子どもも住みやすいまちです。
働くことと暮らすことを分けず、「まち全体で支える」視点がもっと広がれば、加賀市の魅力はさらに高まるのではないでしょうか。
農業と自然の継承
加賀の農業は、地域の風土や文化、人と自然の営みが織りなす大切な財産です。
加賀野菜、地元のお米、伝統的な農法など、今も地域の誇りとして守り続けられています。
ただ、農家の高齢化、後継者不足、耕作放棄地の増加など、地域独自の課題も積み重なっているのが現状ではないでしょうか。
大規模化・効率化の流れは重要ですが、小規模農家や多様な農業の形を守ることも同じくらい大切です。
地元産直、農福連携、直販支援など、地域にあった支援策を広げていくことで、守れる農があるのではないでしょうか。
加賀の里山、棚田、湧水、伝統野菜。
これらを支えているのは、無農薬・減農薬、循環型農法といった、自然と調和する営みです。
環境負荷の少ない農業を選んだ農家を応援する制度、もっと整えていけるのではないでしょうか。
学校給食や家庭で地元産の食材を口にすること。
それは、食べものの背景や作り手の想いを知り、食の大切さを学ぶきっかけになります。
子どもたちが地域の農と自然に誇りを持てる機会、もっと広げていきたいと感じています。
農業は農家だけの課題ではありません。
消費者、飲食店、学校、観光業、移住者、地域全体が関わるテーマです。
皆で「加賀らしい農業」を話し合い、未来の形を描く場をつくること——それが今、必要なのではないでしょうか。
スマートシティ構想と地域主権
加賀市では、自動運転バス、IoT農業、ブロックチェーン都市宣言、デジタル田園健康特区など、全国でも注目される先進的な取り組みが進められています。
この挑戦は、加賀市の強みであり、誇りでもあります。
だからこそ私は、「誰の暮らしにどのように役立っているのか」という視点を、もう一歩深めて考えていきたいと感じています。
デジタル化の恩恵は大きいですが、「一部の人や企業に偏っていないか」という不安も一部では聞かれます。
市民のデータ利用やサービスの公平性、行政の説明責任を、これからもっと丁寧に見直せるとよいのではないかと考えます。
高齢者や障がいのある方、周辺部の住民も、デジタルの恩恵を実感できているか。
「使える人だけが得をする」仕組みにならないよう、支える仕組みづくりがもっと必要ではないか。
私はその視点を、これからの加賀市にとって大切にしたいと感じています。
官民連携やタウンミーティングが行われてきたのは素晴らしいことです。
けれども、「もっと多様な人が参加できる形」は作れないだろうか。
若者、子育て世帯、働く世代も含め、さまざまな市民の声が届く仕組みを一緒に考えていきたいです。
スマートシティは、国や企業主導のものではなく、地域主権の視点で進めることが大切です。
そのためには、「私たちの地域では何が必要か」「何を選び、何を選ばないか」を、市民一人ひとりが問い、話し合える土壌を育てていくことが必要ではないでしょうか。
市民の声と行政の距離
加賀市では、市民参加の仕組みとしてタウンミーティングや意見募集などが設けられています。
これまでの努力は大切な一歩ですが、「自分の声が本当に届いているのか」「意見を言える雰囲気があるのか」と感じる市民もまだ少なくないのではないでしょうか。
市民が気軽に意見を言える場は、十分に用意されているでしょうか。
若者や子育て世帯、仕事で忙しい人も参加しやすいオンライン意見箱やテーマ別座談会など、参加の形を広げる余地はあるのではないかと感じます。
市民の声を聞くだけでなく、「その声がどう政策に活かされたか」を伝える仕組みも大切です。
意見を出した人が「無駄じゃなかった」と思える、そんな行政の姿勢を作れるのではないでしょうか。
行政が市民の声を聞くだけでなく、「こんな課題があります」「こんな工夫をしています」と発信することで、市民側も学べる機会が生まれます。
双方向の対話をもっと広げていけると、行政と市民の距離は近づくのではないでしょうか。
防災と気候変動への対応
2024年の能登半島地震をきっかけに、加賀市でも防災への関心が高まりました。
行政による避難計画や防災訓練の強化は進められていますが、いざという時、「本当に命と暮らしが守られるか」との不安を抱える方は少なくありません。
私は、地域の目線で一歩ずつ見直していくことが必要だと感じています。
女性、高齢者、子ども、障がいのある方、外国人、ペットと暮らす方。
それぞれに異なる支援が必要ですが、避難所体制が一律では十分な配慮が行き届かないこともあります。
福祉避難所の充実、ペット同伴避難の仕組みなど、課題はまだ残っているのではないでしょうか。
ハザードマップや避難ルートは整備されていますが、住民一人ひとりが内容を理解し、行動に移せる状態でしょうか。
防災ワークショップや地域ごとの小規模な訓練、対話の場づくり——こうした積み重ねが必要ではないかと考えます。
気候変動により、豪雨、猛暑、洪水、土砂災害のリスクは年々高まっています。
私たちのまちは、環境整備だけでなく、自然環境の保全や水循環の管理といった視点も必要ではないでしょうか。
防災と環境を一体で考えるまちづくりが求められていると感じます。
結局のところ、いざという時に人を助けるのは、人とのつながりです。
普段の声かけ、見守り、地域の小さな集まりを行政として支えることはできないか。
防災を、物資や施設だけではなく、「人と人の関係性」から見直していく必要があるのではないでしょうか。